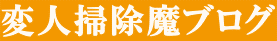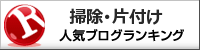田植えと無縁の皆様、こんにちは ^^
田植えの準備の1つである『畔(あぜ)塗り』をご存知ですか?
畔塗りとは、田んぼと畔の境目に、畔から水が漏れないように田んぼの土を塗り固める作業のことです。これが畔で、これが田んぼと畔の境目。

この境目に、下の写真のような感じで田んぼの土を塗り固める作業を『畔塗り』といいます。簡単に言うと、田んぼに貯めた水が漏れないようにするための『土の堤防』みたいなものです。

この畔塗り、できた状態を見ると簡単そうですが、やってみると意外と難しい。今回、ぼくは、農業の大先輩であり師匠である『変人掃除魔わか先生の父』の指導を受け、畔塗りに挑戦しました。初体験です。
畔塗りのやり方
まずは、畔から15cmほど離れた位置をズボズボと歩いて溝を作ります。

溝ができたら、畔側の土の上に反対側の土を鍬(くわ)ですくって乗せていきます。

土を乗せたら、今度は田んぼに入って、鍬(くわ)で土を押し当てて固めながら、斜面になるように土を塗っていきます。

斜面になるように土を塗ったら、塗った部分を平らにならします。あとは、上の部分を鍬で平らにならしたら、畔塗りの完成!

な~んだ、簡単じゃないか。塗るだけでいいんでしょ。楽勝楽勝。な~んて思いました。しかし…。現実は、そんなに甘くなかった。
悲劇の幕開け
まずは、ズボズボと田んぼの中を歩いて、溝を作る作業。
田んぼの畔なんて、普通に歩けば、端から端まで1分もあれば十分に歩ける。しかし、この作業は、1足ずつ歩かなければならない。しかも、めっちゃ歩きにくい。歩いても歩いてもゴールまでの距離が縮まらない。でも、体力を消耗するわけじゃないので、気長にやれば楽勝です。
無事に端までゴール!
自分で言うのは何ですが、いい溝ですな。
曲線が美しい。

さて、次は、鍬で土を乗せていく作業です。
「これは歩くのより楽勝だ!」
な~んて思ったぼくがバカでした。田んぼの土は、水分たっぷりなので意外と重い。しかも、土が鍬に貼り付いて上手く乗せれない。父は簡単そうに乗せていたのに…。この道何十年のベテランと素人の技術の差を見せつけられた感じがします。楽勝だと思っていただけに、ちょっと悔しい。
悔しいだけならまだいい。中腰で延々と続く作業のため、腰が痛い。腰を伸ばそうと思っても、曲がった状態で固まったような感じがして、痛くてサッと伸ばせない。
そんな状態の中、なんとか土を乗せ終えました。

次は、斜面になるように、ペタペタと土を塗り固めていく作業。
「左官みたいで楽しそう!」
一番楽しみにしていた作業が、一番の悲劇を生むとは、作業が始まるまではこれっぽっちも思いませんでした。
田んぼの土を下から上に押し上げるようにして塗る作業は、見た目以上の重労働。だって、強く押し当てるようにして塗らないといけないのですから。しかも、またもや中腰作業。鍬を持つ手には、自然と力が入り、手の平は豆だらけ。めっちゃ痛い。更に、上腕の筋肉はパンパン。
ぼくの顔から、笑顔は完全に消えました。あまりのしんどさに、塗っているところの写真撮影を忘れてしまいました。大失態。ブログのことは完全に忘れていました。
「あともう少しだ。上を平らにしたら完成だ。頑張れ」
自分で自分を励ましながらの畔塗り初体験。
なんとか完成しました。
やったぞー!


田植えと無縁の皆様。
お米は、スーパーでお金を出せば簡単に買えます。だけど、お米を作る方は、めっちゃ大変です。ぼくは、畔塗り作業で、田植えの準備の大変さを体で知りました。
あ、田植えの準備は、これで終わりではありません。このあと、水を貯めて土を掻き混ぜる『代掻き(しろかき)』という作業があります。それが終わって、約1週間後に田植えです。
お米の収穫までは、まだまだ遠いですよー!